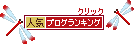[素掘り隧道滝から落差30mの滝まで]
以前、素掘り隧道から落下する滝として松山市の不動滝、海岸段丘滝として徳島県牟岐町の白滝等を紹介したが、海岸段丘にある素掘り隧道から落下する滝が高知県土佐清水市の足摺半島にある。武市伸幸氏の著書に掲載されている落差30mの千万滝の滝壺に向かう途中にある、砂浜に落下する滝である。隧道と滝の規模は不動滝の半分以下だが、隧道内に入ることができ、滝の天辺から海を見下ろすことができる。
それらの滝は大谷地区にあるのだが、そこに行く前、布地区にも小さな滝があるのでそれから紹介したい。アプローチはまず、四万十市間崎で国道321号から県道343号に左折する。尚、以前も解説したように、高知市方面から土佐清水に向かうには、黒潮町の道の駅ビオスおおがた裏の道路、若しくは下田ノ口で県道42号に左折後、広域農道を辿って四万十大橋を渡り、国道321号に出れば、信号も交通量も少なく、オービスもないので早く到達できる。
県道343号は途中で市道に変わる(現在は県道のままかも)が、土佐清水市に入ると再び343号となる。が、立石集落でまた市道に戻る。集落に入って右手に最初に現れる民家(立石八幡宮手前)前のY字路を左に折り返すのだが、この道は対向車が来ると退避できないので、一旦立石川橋を南に渡って適当な路肩を探して駐車し、引き返した方が良い。その道路は帰路、辿ることになるので歩きのロスにはならない。
前述のY字路よりの道路終点(上の地図)から浜に下り、南下して行く。立石川河口は砂浜によって堰き止められ、池のようになっている。最初の谷(立石川支流を除く)入口の岩場には雨後や長雨時期、小さな滝が懸かるが、これは通称「コウラの滝」(2枚目の写真)。
道路終点から30分ほど南下した地点にはコウラの滝よりも絶壁の「長谷の滝」(上の写真は下滝)が懸かっている。但しこれも落差は10m以下で水量も極めて少なく、滝壺も猫の額ほどで、水流も波打ち際に達する前に伏流になっていたと思う。
滝の左岸(北岸)から滝の天辺に上がれる(上の写真)が、そこに上がるとすぐ上流にもう一つの滝(下の写真)がある。先程の滝とこの滝を合わせて長谷の滝という。上段の滝は景観的にもっと滝らしい。
ここから来た道を引き返すのでは面白くないため、回遊する。上段の滝から更に上に踏み跡が続いており、沢が分岐する箇所の上方にロープが垂らされているので、それを掴んで尾根に上がる。
その後、作業車道に出る。いくつか分岐があるが、「上り」の道を選ぶ。しばらく進むと小屋が複数ある畑に出て、西に進んで行くと四国のみちの道標が建つ林道(地形図では破線)に出る。ここは144m三角点峰の南東にあたる。後はこれを北に下って行くと立石集落に戻りつく。途中、太平洋の展望が開ける箇所がある。
次は車で足摺半島東部海岸の大谷地区まで移動する。当方は武市伸幸氏が著書の千万滝の項で紹介していたコースを往路下りたが、その駐車場所(上の地図)は一台分しか駐車スペースがなかったため、お勧めできない。駐車するなら県道27号の大谷西口バス停から南方の適当な路肩が良い。
武市氏のコースは、田中たばこ店跡(道路縁にたばこの看板が立てかけられている)から南に二本目の車道の三差路を東に折れる。この道は更に分岐を過ぎると未舗装の悪路になる。道が左急カーブになった地点の右手に浜への小径が下りている。
浜に下り立った地点の南側には堤防跡があるが、ここは港跡。この堤防付け根に隧道から滝が落下している(上の写真)。落差は10m未満だが、水量は多く、水流は海へと流れ込んでいる。
当初、隧道に上がる道の存在を知らなかったため、もう一つ南の谷に懸かる千万滝へと向かった。千万滝は流石に落差が30mもあるため、見応えがある。上の写真で見るよりも水量はあり、浅い滝壺を経て水流は海へと注ぎ込んでいる。武市氏がこの滝の存在を’90年代初頭までに把握していれば、間違いなく「こうち滝100選」に収録していたであろう名瀑である。
ここより南方にも滝はないものかと、浜を流れる音無川(上の写真)を渡渉して行ったが、落差3mほどのものや、激流の沢(下の写真)があった位。
帰路は音無川右岸の道を登って県道27号に出たが、皆さんは前述の堤防の付け根に上がり、そこから続く道を登れば良い。
ほどなくその道は沢を木橋で渡るが、その橋の下に隧道が開口している。しかしなぜこんなすぐ浜の上に隧道を掘ったのかは謎。港に至る道が沢の出水で崩れないようにしたものなのか。
隧道内は増水していなければ短靴でも歩くことができ、滝の天辺から海原を望むことができる。但し、スタンス(足の置き場)とホールド(手掛かり)は慎重に。
道に戻って上りを再開すると、滝状の流れを経てまたもや直瀑の滝(下の写真)が現れる。落差は十数メートルで滝壺の形もしっかりしており、景観的には山中の滝と変わりない。この滝も名称がついていないようなので、「大谷の滝」と仮称したい。先程の隧道滝は「大谷隧道滝」と。
民家前の道路に出ると西進し、突き当たりは北に折れる。この道は県道の大谷バス停のやや北方に出る。
これらの滝を探訪した翌日、愛媛県第二位の落差120mの滝を探訪したのだが、いずれまたレポートを投稿したい。
すぐにでもその投稿をしてほしい、という方は次のバナーをプリーズクリック。