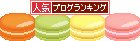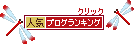≪坂本龍馬の御手洗滞在所≫
若胡子屋の斜め向かいが先般より触れている、龍馬がいろは丸衝突沈没事故の件で紀州藩と長崎で交渉すべく、瀬戸内海を船で西進している際、潮待ちで宿泊した金子邸で、屋号を三笠屋という。庄屋でもあった。
鳥取藩士、河田左久馬の書簡に、慶応3年4月30日、潮待ちで御手洗に滞在していたら、偶然、龍馬も上陸し、談笑した旨、記されている。
龍馬はこの後出港すると下関に寄り、三吉慎蔵に、自分に万が一のことがあれば、お龍を土佐におくり届けて欲しい旨、依頼している。つまり、龍馬は紀州藩関係者に暗殺されるかも知れないと思っていたのである。
いろは丸事故についてはこの後、龍馬 ら海援隊側に有利な措置が取られたが、龍馬が京で暗殺された後、慎蔵は奇しくも前述の約束(=龍馬の遺言)を果たし、お龍を土佐へ送り届けることになる。
ら海援隊側に有利な措置が取られたが、龍馬が京で暗殺された後、慎蔵は奇しくも前述の約束(=龍馬の遺言)を果たし、お龍を土佐へ送り届けることになる。
この金子邸では、龍馬が暗殺されてから11日後、御手洗港で合流した長州藩軍と広島藩軍による御手洗条約が締結されている。長州軍には当然、奇兵隊と第二奇兵隊が含まれている。締結の翌朝、長芸 連合艦隊は倒幕のため、出港して京へ向かった。
連合艦隊は倒幕のため、出港して京へ向かった。
余談だが、近代、金子家当主は御手洗郵便局長を務めていた。当時の郵便局は金子邸の裏手、現在のJA広島豊御手洗支所の地にあった。
ここの金子家か大長の金子一族かは分からないが、関 西の某大学の金子教授はその子孫である可能性がある。本人は論文で自分は広島県の離島の出身で、伊予の金子備後守の子孫であると述べていた。三笠屋の金子氏と大長の金子一族が備後守の末裔であることは、島の郷土文献で確認している。
が、この前触れた、龍馬に資金援助を行って いた金子氏は大崎下島の系統の金子一族ではない。
いた金子氏は大崎下島の系統の金子一族ではない。
今日、戦前に発行された全国の金子一族に関する古書を注文したが、それに記述されていれば助かる。
金子邸の南西の道路向かいにあるのが、「ももへの手紙」に描かれていた天満神社。ももが、サンダルが脱げながら走って参道を逃げていた。それを追う妖怪の一人は、鳥居をくぐらず、玉垣を乗り越えてももを追っかけていた。新興宗教団体の中にも、鳥居をくぐってはならない、という思想を持つものがあるが、そういう輩は妖怪並の心根なのだろう。
参道脇には菅原道真公の巨大な歌碑が 建立されているが、この碑と碑の解説板も描かれていたと思う。
建立されているが、この碑と碑の解説板も描かれていたと思う。
本殿右横には、道真公が大宰府に向かう折、潮待ちで御手洗に滞在していた際、手を洗った「菅公の井戸」がある。この井戸は元々あったのではなく、菅公が持っていた笏で地面を掘ったところ、清水が湧き出たのだという。それが「御手洗」の地名の由来である。
本殿下は通路になっており、これを「可能門」という。願い事を一つだけ唱えながらここをくぐれば、それが叶うという。大崎下島随一のパワースポットだろう。
菅公の井戸から可能門を抜け、そのまま北上して道路に出れば、神社境内を回遊したことになる。
龍馬と関わった金子一族を明らかにしてほしい、という方は次の二つのバナーをプリーズ・クリック
 にほんブログ村
にほんブログ村












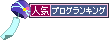























 ヒデタ樹 スーパー・ベスト~海のトリトン/人造人間キカイダー~
ヒデタ樹 スーパー・ベスト~海のトリトン/人造人間キカイダー~ Heavy Metal: Music From The Motion Picture
Heavy Metal: Music From The Motion Picture 田村英里子 ゴールデン☆ベスト
田村英里子 ゴールデン☆ベスト Myこれ!クション 早坂好恵 BEST
Myこれ!クション 早坂好恵 BEST 渡辺典子 ベスト
渡辺典子 ベスト 〈ANIMEX 1200シリーズ〉(14) 夢戦士ウイングマン 音楽集
〈ANIMEX 1200シリーズ〉(14) 夢戦士ウイングマン 音楽集 海の青~Singles And More~(DVD付)
海の青~Singles And More~(DVD付)















 一期一会 プレミアム ベスト
一期一会 プレミアム ベスト