(1) 黒沢(くろぞう)湿原[徳島県三好市]
「四国の尾瀬」及び「サギソウの湿原」として有名な湿原。標高550m前後、南北2キロ、幅100~300mの細長い湿原。昔からオオミズゴケが生息していたが、水田だった時期もある。
シラサギが飛ぶ姿にそっくりのサギソウは自生のものは既になく、湿原内にある「サギソウ園」は植栽されたものだが、シーズンには人里離れた山の上であるにも拘らず、大勢の行楽客が訪れる。
年間を通して何十種もの植物が開花する。トキソウ、ヒツジグサ、キセルアザミ、ホソバリンドウ等々。
南端には小振りのたびの尻滝もあるが、無名峰ピークハンターは黒沢山(614.3m)から605mピークまでの尾根道と湿原遊歩道をセットにして回遊できる。地形図は「阿波川口」。
関西で有名な湿原と言うと京都の八丁平が思い浮かぶと思うが、周辺景観に於いては八雲ケ原の方がはるかに優れている。
コヤマノ岳(1181m)東側の標高900m前後に広がる湿原。井上靖の小説で知られる「比良のシャクナゲ」も咲く。他にもベニドウダンツツジ、レンゲツツジ、ジュンサイ、ヒルムシロ等々 。
。
比良登山リフトの廃止に伴い、比良スキー場やロッジ、ヒュッテ等も廃業したため、登山客のみが訪れる地となっているが、昭和期、各種施設建設によって埋め立てられた部分も近年、湿原として復元されつつある。
南東の北比良峠付近からは琵琶湖のパノラマが広がる。
石鎚山系筒上山南西の1399mピーク下に広がる、西日本では超高層湿原となる。
30m×40m位の地にウマスギゴケがビロードの絨毯のように敷き詰められている。
夏場、ウマスギゴケに顔を近づけてみると、2~3ミリほ どの花が咲いているのが分かる。
どの花が咲いているのが分かる。
普段、水がないことが多いが、雨後に訪れると 水の溜まり方が非常に神秘的。
登山口(石鎚スカイラインの金山橋西袂)には文字が消えかけた小さな手製の道標しかない(‘04年時)にもかかわらず、休日、登山口前広場は登山客のマイカーで溢れる。
 山と高原地図 54 石鎚・四国剣山 2012
山と高原地図 54 石鎚・四国剣山 2012
失言で失敗したため、気分晴らしに「湿原」でも行ってみよう、と思った方は次の二つのバナーをプリーズ・クリックon

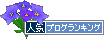 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

 山と高原地図 45.比良山系 武奈ヶ岳2012
山と高原地図 45.比良山系 武奈ヶ岳2012