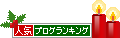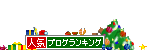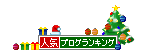[坂本龍馬が訪れた赤岡の寺院跡]
(※11ヶ月ぶりのシリーズ再開)
小松与右衛門邸の街道を挟んだ向かいには、カトリック赤岡教会(聖ヨゼフ教会)があるが、これは龍馬と交流した須藤楠吉と間接的に関係がある。
以前解説したように、楠吉は西浜の浦上キリシタン獄舎の牢番を買って出て、キリシタンらの世話を献身的に行った。それは明治政府や高知藩(明治、土佐藩から高知藩になる)の都合で、自らの寺を廃寺にされ、還俗させられたことから、迫害されるキリシタンの辛さが分かるからである。
地元民も賤民として長い間差別されてきたこともあり、キリシタンに同情し、また、その揺るがない固い信念を貫く様を尊敬の念をもって見ていた。その時、赤岡にキリスト教信仰の種が蒔かれた。
時を経て昭和7年、信仰の種は開花する。西浜獄舎の浦上キリシタン殉教(十数名が病死)を記念して、この地に教会が建設されたのである。当時はキリシタン投獄のことを知る者も生存していたことから、感慨もひとしおだったことだろう。
尚、教会の建物は昭和末、改築されている。確か、敷地内に保育園か幼稚園があったように思う。寺院でも境内にそれらの施設を建設するケースが全国的に見られる。
さて、その龍馬も訪れたことのある楠吉が住職を務めていた寺だが、跡地は伊能忠敬の旧測量地跡の十字路を北に入った突き当たりにある。赤岡小学校がその跡地である。
その寺、正福寺は以前触れた与楽寺の末寺で、山号を有せず、来歴も詳らかではない。ただ、赤岡を領していた、武田信玄と先祖が同じ土豪で土佐七守護の一氏、香宗我部氏が創建し、寺領30石を寄進したことは分かっている。
境内は東西20間、南北23間の規模で、本堂以外にもいくつかの堂宇があったが、地蔵堂のみ、祠の如く規模が縮小され、校舎南東の移設された墓地の隅(墓地の北西隅=体育館北側)に寺の手水鉢と共に残っている。その手水鉢は龍馬も使用したことだろう。
地蔵堂の南には、赤岡初の私塾・北固塾を開設した漢学者、田宮宇内(うない)の墓が移設されている。赤岡の郷士の家に宝暦11年、生まれたが、成人後は江戸に遊学して教史、詩文を学び、その後、摂津に下って幕府官許の学問所・懐徳堂で学んだ。
その後、京都四条で塾を開いたが、3年で赤岡に帰郷。文化13年、北固塾を開き、教書や書道を教えた。
墓碑の銘は土佐藩校・教授館の学頭でもあった日根野鏡水(弘亨大卿)による。鏡水の先祖は豊臣から徳川家に仕え、延宝5年、土佐藩に仕官した。
尚、鏡水と日根野道場の日根野弁治の先祖が同一かどうかは資料・文献が散逸しているため、定かではない。
体育館の建つ地は大立寺跡で、安永年間、与楽寺末寺・持宝坊が寺に昇格して改称した。元は裏町にあったが、宝永5年の赤岡大火災で焼失し、10年後、再建された。明治11年、この地は香美郡役所となり、その後、赤岡町役場と変わった。戦後は赤岡簡易裁判所が新築され、平成26年、現在の体育館が建った。
このようにこの地は歴史の変遷を経ていることから、「歴史の丘公園」として整備され、東隣の検察庁跡に休憩所が設けられている。
因みに、小学校の南側石垣の一部も正福寺当時のものである模様。
PS:今年は病名が分からぬまま、睡眠時無呼吸症候群に苦しめられていたため、記事作成に長時間かかる(各種文献も読む必要があるため)龍馬等歴史関係の記事は殆ど投稿しなかった。
昨日から本格的治療を開始したため、今後は他の休止中のシリーズものも再開できるかも知れない。但し、予定は未定。
他の龍馬のシリーズも再開してほしい、という方は次の二つのバナーをプリーズ・クリック。











































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15621499.522059e2.1562149a.e2e5a261/?me_id=1256987&item_id=10010195&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fb-side%2Fshouhin-image%2Faz02%2Faz-50111_01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fb-side%2Fshouhin-image%2Faz02%2Faz-50111_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)