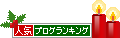[琴弾公園・巨石付近の「笑い猫」]
希望の党は公約とは別に将来実現させる政策として「希望への道しるべ~12のゼロ~」を発表した。隠ぺいゼロや満員電車ゼロ、花粉症ゼロと共に注目すべき政策がペット殺処分ゼロ。私も前から殺処分ゼロにするための有効な方法論と施設(「完璧な」動物愛護センター)を考えており、それが高知県にあればいいと思っているが、自民党政権下と県の経済優先主義では叶うことはないだろう。
私の方法論は後述するとして、今回は県外、香川県観音寺市の野良猫名所を紹介したい。それは以前、江甫草山防空監視哨跡(→江甫草山防空監視哨跡(観音寺市))の記事で触れた有名観光地・琴弾公園である。
琴弾公園は「日本の地上絵」銭形砂絵(上の写真は真横から見た所)が有名だが、公園駐車場(下の写真)付近や園内の東屋、その駐車場と琴弾八幡宮との中間にある琴柱池北の山際等で野良猫を見かけることが多い。公園駐車場は結婚式場を擁するホテル前にあることから、餌場は設けていないにしろ、野良猫は周辺住民に可愛がられているのだろう。
防空監視哨跡の記事でも紹介した琴弾山の天狗山展望台へ到る九十九曲道登山口北側にも東屋風の「山口井戸」があり、一才未満と思われるキジトラ(下の写真)がいた。山口井戸は大同年間(806~810)、弘法大師空海が観音寺の住職時、地域住民が旱(ひでり)続きで水不足に悩んでいたため、掘ったもの。
山口井戸から西側の芝生区域にも白猫がおり、餌をあげている間は触らせてくれた。
住宅地図には山口井戸方面への道と駐車場への道との三差路のやや手前に「獅子の口岩」が表記されているが、道路が二車線化された際、消滅した模様。以前紹介した三重県の「東洋のスフィンクス」のようなものだったのだろうか。
琴柱池は中央の島が両岸の橋で繋がれた景観の優れた場所だが、ここに顔が常に笑っているように見える猫がいた。当初は当方のことを警戒していたが、その北側の山際にいた猫たちに餌をやっていると近寄ってきて、撫でさせてくれた。やはり笑顔の似合う猫に悪い猫はいない?岩合光昭氏に撮りに来て欲しい。
ところで、その猫たちが歩いていた山際のコンクリート縁の東方には巨石「問答石」がある。複数の大石や岩からなるもので、ピラミダルな岩塔がある他、注連縄が掛けられている石は岩から分離して立岩となっている。
琴の音を出す小船に乗った宇佐大神と神宮寺の日證住職が問答を行った石だと言われている。
巨石はこれだけではない。問答石東の琴弾八幡宮境内に建つ山之神神社社殿右側にも屋根ほどの高さの立石がある。この石、不思議なことに下部に穴が貫通している。この石は見る角度によって形が変わるが、背後に回るとガメラに出てくる怪獣・ギロンのように見える。
また、前述の記事では源義経が琴弾八幡宮に奉納した「木乃鳥居」も触れたが、それは次のようなことによるもの。寿永4年の屋島合戦時、平家軍の総大将・平教経は劣勢を挽回すべく、伊予の大洲城主・田口教能が率いる一千騎が到着すると源氏軍を海と陸から挟み撃ちにする作戦を企てていた。
しかし義経は夢での暗示からこの作戦計画を知る。そこで側近の伊勢三郎義盛に、教能が屋島に到着する前に接触し、進軍をやめるよう説得させることにする。三郎は万が一説得に失敗した際は討死する覚悟で、鎧の下に死に装束を着込んで浜沿いを走った。
三郎は琴弾山で教能軍と出会い、教能と十王堂で会談し、平家軍は大敗し、教能の父・重能も降参した旨、説いた。この嘘を真に受けた教能は軍を解き、源氏の軍門に下った。このことにより、屋島合戦は源氏軍の勝利となったのである。三郎が説得に失敗していたなら、歴史が変わっていたかも知れない。上の写真と下の地図が木乃鳥居。
前述記事では琴弾山と東麓の四国霊場を回遊する独自に見出したコースを紹介したが、69番札所・観音寺から道路を北西に進み、根上り松から興昌寺山(山上に古墳)と興昌寺を回遊後、観音寺中学校から銭絵に出ると歩き甲斐のあるコースになる。根上り松は根元が男根(包茎)のようになっている。
さて、冒頭で触れた殺処分ゼロにするための方策だが、高知県には動物愛護センターがないので、まずそれを造る。現存の施設では乳飲み子猫は即日殺処分しているが、そういう子猫を育てるため、小動物看護士資格を持つ職員を常駐させると共に動物保護のNPOやボランティア等と協力し、乳飲み子猫を育てる体制を作る。ボランティアの取り纏めはNPOに委託してもいいだろう。生後二ヶ月位まで育てるのは重労働となるため、ボランティアは有償として費用は県が支出する。
野良猫犬を増やさないため、ペットを捨てた飼い主には罰金として1万5千円支払わせる。支払いを拒めば預金等を差し押さえる。そして密告通報制度を取り、ペットを捨てた飼い主情報を報告した者にはその1万5千円の内、5千円を謝礼金として支払う。
当方が望むのは、この世から野良猫スポットがなくなり、全てのペットが幸せな生涯を送ることができる世界である。
PS:最近、観音寺市内で第二、第三の「香川のウユニ塩湖」(幻想的な鏡面の水面)を見出した。しかし大潮や中潮の干潮時は不適のため、どのような引き潮時が適しているのか考察中。正月に何日か泊って確認しようと思う。適期が判明すれば観音寺市の観光の目玉になることだろう。
高知や愛媛のウユニ塩湖も発見してほしい、という方は次のバナーをプリーズクリック。



































































































































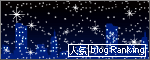



















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/164613a7.9b49f171.164613a8.5c0af99e/?me_id=1310041&item_id=10026557&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fefiluz%2Fcabinet%2F04657996%2F05905774%2Fkz07042_01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fefiluz%2Fcabinet%2F04657996%2F05905774%2Fkz07042_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)