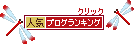[戦争遺跡・かまぼこ型壕と素掘り壕群]
拙著等で米軍は昭和20年10月30日、鹿児島県南部から本格上陸する(11月1日)前の陽動作戦として、高知県に上陸する計画を立てており、日本軍もそれを察知し、高知海軍航空基地の西方の山並みに縦深に陣地を築いていたことを述べた。
拙著では最も海岸に近い琴平山陣地、ブログでは秋葉山の片山トーチカ群、ヤマケイサイト投稿記事では大森山から蛸ノ森(147m)周辺尾根の陣地について解説した。未探訪だが、海軍向山高角砲陣地へ通じるルート沿い北側の森にも陸軍陣地があることを机上で確認している。
![]()
琴平山と蛸ノ森から北東に伸びる尾根に挟まれる形で、50m峰(当方は勝手に「タンク山」と呼称)を中心とする山塊がある。当然この山塊にも多数の陣地が構築されていることが予想されるが、陣地構築のセオリーから言えば、横穴陣地等を掘るなら、東方に開ける谷部である。よって、二ヶ所の主要な谷を調査し、南側の谷沿いにかまぼこ型のコンクリート壕を発見した。
この壕に一番近い連隊本部は、蛸ノ森に近い御旗山で軍旗を奉焼した陸軍第12連隊である。
![]()
蛸ノ森トンネル工事前の公的機関による自然生態調査に於いて、調査員からかまぼこ型のコンクリート壕があった旨の報告を受けたことがあるが、トンネルが通る尾根からは離れているため、今回の壕とは別だろう。
[コース]
南国物流団地北端の十字路を西に折れる。突き当たりには野尻公民館があるが、この西の歩道と立入禁止の私道を合わせた四差路が上り口(下の地図)である。付近に駐車スペースがないため、当方は物流団地内の適当な路側帯に駐車した。
北方の山口団地から南下する方が近いが、駐車場所に苦慮するのではないかと思い、逆側から北上した。
コースは前述の歩道を北西に進む。最初の谷の分岐では北に進むが、その最初の谷にも無数の横穴壕や塹壕が掘られている。
次の谷の分岐には小屋が建てられているが、この小屋沿いの小径を西進すると支流の谷(水流はない)が左手に分かれ、そこからかまぼこ型壕が見えている。
![]()
因みに当方は最初、この谷にコンクート壕があることは知らなかったため、小屋の分岐のすぐ北の四差路を北西に登り、谷沿いの壕群を巡った後、稜線に上がり、タンク山のタンク前身の貯水槽跡から若宮八幡のピークへ登った後、タンク手前のY字路を南西に進み、タンク南方尾根から前述の最初の谷に下り、各所の壕を確認後、小屋から西の道に入った。勿論、コンクリート壕の存在は知らずに入山したため、支尾根の上り下りを繰り返し、3時間ほど経ってようやく「目ぼしい戦争遺跡」を発見するに至ったのである。
かまぼこ型壕近くの道は不明瞭だが、手前には兵舎か何かの基礎(下の写真)が残っている。壕の扉(木製か鉄製かは不明)は終戦時の需要で、地元民が持ち去ったのだろう。壕内は以前紹介した須崎市の山崎鼻トーチカ程度の広さで、西側側面上部に銃眼のような形状の小窓、天井には排気孔が開いている。四角いオイル缶のような残骸が残っているが、これが戦時中のものか否かは定かでない。物資保管壕なのか退避壕なのかも不明である。
踏み跡は奥へと続いているが、当然その奥にもいくつも素掘り壕がある。
![]()
ところで話は変わるが、県内の戦跡調査をしている主な施設・団体としては、平和資料館・草の家の他に、南国市の高知県立埋蔵文化財センターがあった。担当者は現在の草の家の出原副館長である。60歳で定年を迎え、草の家副館長になったのだろう。
![]()
実はこの人物も草の家の戦跡研究員同様、嘘の理由をつけて戦跡の場所や資料を公開しようとしない。彼と初めて会ったのは2006年の草の家での戦跡勉強会だった。当時は前述の戦跡研究員は「表」に出てきておらず、当方はその存在を知らなかったため、時折、草の家へ出向いていた。
![]()
その勉強会後、出原氏に土佐市の新居城跡の陸軍陣地(下の写真・拙著収録)の場所を尋ねた。幕末の新居砲台跡を調べる過程で、地元に於いてこの情報を得ていたからである。当方は当時、県森林局が立ち上げて民間に委託していたあるブログサイトのブロガーであり、戦争遺跡や廃線跡、登山等の記事を投稿していた。
![]()
出原氏には「県内の戦跡の詳細を公開している書籍やホームページが少ないため(当時)、当該地域の歴史を後世に伝えていくためにも、未公開の戦跡を発掘していきたい」旨、伝えたのだが、なかなか教えてくれない。
![]()
あまりにも頑なに答えてくれないため、三度目に尋ねた時、「詳しい場所はいいから、塹壕(上の写真)がある尾根だけでも教えて戴きたい」と言うと、出原氏は面倒臭そうに「あ~もう!ここ、ここ」と地図を指した。
![]()
それから8~9年後、「高知市民大学」の講義で講師だった出原氏(当時は埋蔵文化財センター勤務)に、講義での質疑応答時、宿毛市鵜来島の海軍防備衛所の資料(出原氏が東京で入手)について閲覧させて戴きたい旨、申し出ると、いきなり挙動が可笑しくなり、「し、資料はどこかに紛失して分かりません」と答えた。当方は’90年代、探偵・調査業を行っていたから、このような嘘はすぐ分かる。
![]()
その嘘の証拠が今年の高知新聞の記事である。防備衛所の資料を紛失したと言っていた出原副館長が鵜来島へ調査に行っていたのである。つまり、資料は紛失しておらず、きっちり保管していた訳である。
前述の戦跡研究員と言い、この副館長と言い、なぜ高知県の著名な戦跡研究家は皆、嘘までついて戦跡を公開せず、戦跡の普及を阻害するのか。なぜ後世に伝えようとしないのか。そこまでして自らが調査した戦跡を自分だけのものにしたいのだろうか。
その戦跡研究員は民間人だが、出原副館長は当時、県立施設の職員である。埋蔵文化財センターのような生涯学習に関わる施設は博物館や教育委員会同様、リファレンス業務は職務の一つである。それについて虚偽を言ってまで行わない、というのは職務怠慢にほかならない。
高知県の戦跡普及活動は私が一人で行わなくてはならないのだろうか。
高知県の全ての戦跡調査者は考えを改めるべき、と思う方は次の二つのバナーをプリーズクリック。
![]() にほんブログ村
にほんブログ村![]()


























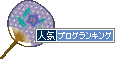









































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15e92d9a.6b8deff5.15e92d9b.3d283f9a/?me_id=1215240&item_id=10017714&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fetoile%2Fcabinet%2F12cd%2F12cd-1017a.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fetoile%2Fcabinet%2F12cd%2F12cd-1017a.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)